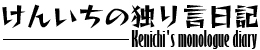第1次感情と第2次感情
現代は、ストレス社会ともいわれており、一部の企業では産業精神保健を導入し、メンタルヘルスによるサポートを行うような時代になっています。
人間は誰しも、顔に出やすい出にくいこそありますが、感情というものに左右されやすいですよね。
実はこの感情なのですが、心理学者アドラーの感情理論によれば、第1次感情と第2次感情とに分けることができるんです。
まず、第1次感情とは、不安/恐怖/辛い/疲れた/悲しい/淋しい/ストレスなどといった感情です。
共通点は、すべてネガティブであり、負担に感じる、あるいは嫌だと思う感情なんです。
次にこの第1次感情から、つながる先には第2次感情があり、相手を責める気持が高くなる、つまり「怒り」の感情だったのです。
怒りのタイプにもいろいろ
最近は、日本だけではなく、世界的に熟年離婚が増えているといいます。
ネガティブな第1次感情は、コップにたまる水のように蓄積されていきますよね。
やがてコップがいっぱいになればあふれてくるように、強い感情である怒りがこみあげてきやすくなるんです。
実は、こうした怒りにも、4つのタイプがあるんです。
『持続性のある怒り』
・過去を思い返し、怒りがこみあげてくるパターン。
『強度が高い怒り』
・激しくい怒り、抑えられないこともあるパターン。
『頻度が高い怒り』
・イライラや不安感により、過敏に反応して怒ってしまうパターン。
『攻撃性がある怒り』
・特定の相手やモノにあたり、モノを投げたり蹴ったりしてしまうパターン。
アンガーマネジメントとは
アンガーマネジメントとは、これまで説明したように、イラつきや怒りといった感情に対して、自身でコントロールする方法なんです。
皆さんの中には、怒りに任せて退社してしまった、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
会社にとっては、有力な人材を手放してしまうのは、デメリットしかありませんよね。
アンガーマネジメントは、衝動的な言動や行動を抑制し、適切な問題解決やコミュニケーションにつなげるための手法なんです。
特に会社などでは、怒りの感情が職場の人間関係の悪化、また雰囲気も悪くさせる原因にもなりますよね。
このような問題を解決するため、最近ではアンガーマネジメントについての研修、セミナーなどの開催も盛んに行われるようになってきたんです。
実際にやってみよう
前項で、例えに熟年離婚を出しましたが、長年の妻のうっぷんがあふれだし、爆発した状態がよくお分かりいただけるかと思います。
会社でも同様で、何度も部下が失敗すると、許されない気持ちで怒鳴ってしまうのも、この第2次感情の怒りのせいなんです。
アンガーマネジメントで、怒りを抑えるコツしては、イライラや怒りを感じたら、6つ数えることを習慣づける。そして、怒りにスコアをつけるのも、有効なのだそうです。
私もそうですけど、最近コロナでイライラも増えてきていますので、家族で早速実践したいと思います。”